タスクフォース会合Q&A
日本技術モデルに関して
- Q1:
- 新築住宅を強制的に省エネ型住宅・建築物にさせることは、建築費用が既存住宅よりも高額になるために 住宅建設自体が敬遠されて、反対に建築市場が冷え込むのでは?
- A1:
- 断熱性の高い住宅は省エネ性が高くなるともに、住宅内部の温度格差が小さくなり ヒートショックの予防になるなど、快適性・健康面にもおおいにプラスである。
温暖化対策のためだけではなく、むしろ豊かな住環境を整備するといった観点から 推進していくべきである。住宅はそれ自体が高額で、なるべくよいものを買おうと
いう意識も強いため、断熱住宅の副次的効果をうまく伝えることが重要である。
また、施工者のトレーニングとともに、高断熱住宅の普及を進めていくことで、工法の工夫、 部材の調達面なども含めて、総合的な価格の低下も期待でき、それは更なる普及の拡大に繋がる。 「建築市場が冷え込み」断熱対策が進まないという指摘だが、費用は裏を返せば市場である。 断熱対策を進めることで建築市場(特に冷え込みの厳しい地方の市場)の活性化と、 国民の生活の質の向上の両立が期待できる。 - Q2:
- 全国どこでも高効率ヒートポンプ給湯器に転換できるという想定は、 寒冷地が灯油に依存していることを考慮しておらず、現実的ではないのでは?
- A2:
- 「寒冷地が灯油に依存している現実を考慮していない」という指摘は 高効率給湯器=電気ヒートポンプ給湯器という読み違いから生じていると考える。
住宅用高効率給湯器には電気ヒートポンプ給湯器だけでなく、 潜熱回収給湯器が含まれており、潜熱回収給湯器には都市ガス、 LPG、灯油向けがある。2005年における灯油給湯器の比率は21%としているが、 2020年にはやや減少するもの16%の比率となっている。 - Q3:
- 次世代自動車以外が販売禁止になると、 日本がこれまで培ってきたエンジン自動車に関する技術の衰退を招くだけではなく、 生産を支える部品産業自体の衰退を招くのでは?
- A3:
- 「エンジン車の生産が海外移転する」とあたかも次世代自動車は すべて電気自動車であるかのような指摘になっているが、 乗用車における電気自動車の比率は▲20%削減ケースでも2020年の販売ベース約2割である。 また、87%(修正後88%)は乗用車の販売ベースの普及率であり、 貨物車は2020年でもほとんどが従来型のエンジン車である (次世代車普及率は2020年販売ベース16%で、電気自動車はその一部のみ)。
- Q4:
- 地方ではまだまだ一人一台とも言われる車社会であるが、 次世代自動車は従来の自動車に比較して高額であることから、 そういった地域でのセカンドカー、サードカーが手に入らなくなってしまい、 生活に支障がでるのでは?
- A4:
- 「地方在住者は安価なセカンドカーがなくなる」との指摘であるが、 次世代自動車の導入率を高める必要があるかどうかは燃費で判断しているので、 軽自動車は相応の燃費であれば、必ずしもハイブリッド自動車や電気自動車でなくてもよい。 一方で、安価なセカンドカーが郊外の自動車中心社会化を誘引したことも事実である。 低炭素社会に向かう上で郊外においても低炭素交通の構築を検討していくことも必要であろう。
- Q5:
- 試算では2030年までのエネルギーコスト削減効果を見込んでいるが、 通常の機器の耐用年数は10年程度であり、20年後まで見た議論には無理があるのでは?
- A5:
- 我々の試算では耐用年数を考慮した計算を行っている。 2010~2020年までのエネルギー費用の削減額については、 この間に導入された技術が、導入から2020年の間において削減したエネルギー費用額を算定している。
2020年以降については機器が退役するまでに削減したエネルギー費用の総和を算定している。
具体的には、耐用年数10年の技術では、2011年に導入された技術は、 2020年までしか効果を発揮しないが、2020年に導入された技術は2029年まで効果を発揮する。 ここで述べているのは2020年断面だけで効果をみるのではなく、 機器のライフサイクル全体の効果をみるということである。 - Q6:
- 2020年までに大幅にCO2を削減するには 再生可能エネルギーを大幅に導入する必要がある、とのことであるが、 コスト負担や実現可能性の観点から慎重な検討が必要なのではないか?
- A6:
- 導入量の想定では必要なコスト、物理的制約、社会的・制度的課題等を 慎重に検討することが必要との点について同意する。 とはいえ、限られた時間の中、「再生可能エネルギーの一次エネ比10%目標の可能性を検討する」という タスクフォースへの要請に応えるため、 ここでは環境省「低炭素社会に向けた再生可能エネルギー普及方策検討会」の検討成果を参考にしている。 今後の検討の中で、再生可能エネルギー普及に関わる問題点を明らかにし、 制約を打破し、再生可能エネルギーを日本の持続可能な成長戦略の一貫として検討していくことが必要となろう。
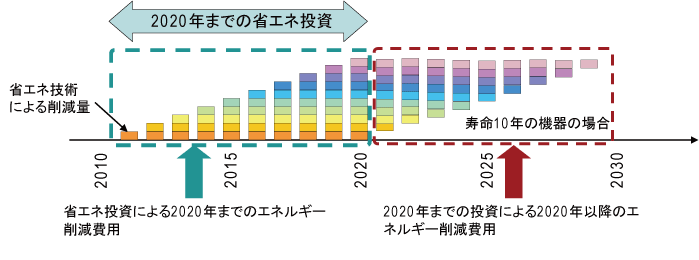
日本経済モデルに関して
- Q7:
- 日本経済モデルの分析結果の挙動がおかしい(特に25%削減ケース)ように見受けられるが、これはなぜか?
- A7:
- いくつかの項目については、不連続が見られるが、 これは、想定されている経済成長率の前提(2010-2020年まで年率1.6%で成長する)と、 真水▲25%の目標が相容れないことを示すものでもある。
特に家計消費支出が真水▲25%ケースにおいて不連続に変化する点については、 経済が縮小するにもかかわらず、目標としている経済成長を達成するためには、
レファレンスと同等の投資が行われることと、多額の税収が家計に還流されることから、 CO2排出量の少ないサービスの消費が増大するために起こっている。
一方、こうした状況は、現実の社会では考えにくく、モデルで計算された結果は均衡解ではあるが、 現実とはかけ離れた状況を再現しており、想定されている経済成長とCO2排出量の削減目標を 同時に達成することが相容れない状況であることを示唆したものであると考えている。 - Q8:
- 財政支出ケースについて、モデル上で倍増した計算を実施した場合はどうなるか? いくらでも負担が減る結果が得られるのであれば、経済モデルによる一般均衡の評価としておかしい。
- A8:
- 環境研の日本経済モデルでは、日本技術モデルの結果である追加費用とそれによる効率改善を前提としている。 財政支出ケースでは、徴収した温暖化対策税の税収を温暖化対策の追加費用
(下図の限界費用曲線の下側の黄色部分に該当)を埋めるために活用するものであり、 全くの空想の話ではなく、技術的な裏付けはきちんととった上での試算である。
このため、財政支出を2倍にしても、組み込むことが可能な対策技術がないので、 負担が同じように減ることはない。 - Q9:
- 名目可処分所得はプラス2.5%と、むしろ対策をしないときよりも増加しており、 それ自体が誤っている可能性が高いのではないか?
- A9:
- これも真水▲25%ケースのみに見られる現象で、現実の社会では考えにくい結果であり、想定されている経済成長を無理矢理達成するために投資を行っていることと、真水▲25%という極めて厳しい削減目標が整合していないことを示すものであるといえる。
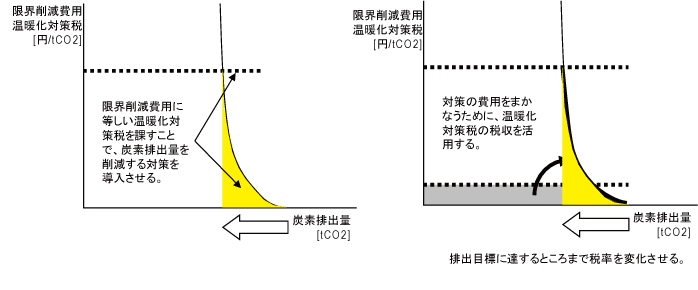
2009年4月までの試算結果と今回の試算結果の違いについて
- Q10:
- 2009年4月までの検討会で提出された結果(18%削減ケース)と、 今回の結果(20%削減ケース)を比較すると、今回の方が対策導入量が減少している。 マクロフレームを変更していないのであれば、対策導入量が減少しているのに CO2削減量が上積みされ、必要なコストがほぼ半減しているのはなぜか?
- A10:
- 前回の削減量(▲18%)と今回の削減量(▲20%)の比較について
▲18%というのは以下の(1)の定義によるものであり、 その指標は今回用いていない。
(1)(2020年CO2排出量 - 1990年CO2排出量) / 1990年GHG排出量
その定義のもと、今回の試算結果を計算すると▲17%となり、 エネルギー起源CO2排出量について対策導入量を減少させていても 前回より2%も削減量が増加しているとの指摘は当たらない。 - コストがほぼ半減している点について
前回の選択肢⑥の費用において大きなウェイトを占めていたのは 既設住宅、既設建築物の改修は効果の割に費用が極めて高い対策である。 前回は、一定の省エネ基準を満たさない住宅・建築物の全て (全住宅の5割、全建築物の4割)を改修するとしていたが、 それでは費用が膨大になるので、今回は1割程度の改修に留めた。 その結果、約90兆円(住宅分80兆円、建築物10兆円)、 投資費用が前回よりも安くなっている。 - 保有燃費の改善について
燃費改善の想定は、前回は50%改善、今回は26%改善と示した。 この燃費改善率は、前回の試算は次世代自動車を含んだ数字で、 今回の数字は次世代自動車を含んでいない数字である。
前回の試算について次世代自動車を含まない従来自動車のみの数字とすると12%改善となり、 今回の26%よりも低い値になる。 また、今回の推計には近年のハイブリッド自動車の販売状況を織り込んだ (今売れているものは2020年に残存し、CO2削減に寄与)ため、 次世代自動車を含んだ全体の燃費改善率は、前回の50%から今回は69%と、今回の方が高い値となっている。 - 対策導入量の比較について
いくつかの対策を緩め、特に温暖化対策の観点から 費用対効果の極めて悪い住宅・建築物の断熱改修を控えるかわりに、 風力発電や自動車対策について深堀したことで、費用的には大きく低減されたが、 削減量はあまり大きく変化していない。
前回と今回とでは、削減率の定義が異なり、かつ自動車の改善率の表現方法も異なっている。 これを統一して比較表を作成すると、下記のようになる。 - Q11:
- 日本経済モデルの分析結果が、2009年4月までの検討会と比較すると、 今回の方が特に実質GDPへの影響と可処分所得の減少幅が縮小されて 経済への影響が小さくなっているように見られるが、これはなぜか?
- A11:
- 実質GDPへの影響について:前回▲6.0% → 今回▲3.5%(▲25%ケース)
4月の中期目標検討会においても、今回と同様に真水▲25%を達成するような 技術の組合せを提示することができなかった。 4月の試算では、日本経済モデルと世界経済モデルの関係を整合的にするために、 日本経済モデルで想定している経済成長率を年率1.6%から1.2%に変更して計算を行った。 これは、4月14日の資料1・添付3や、3月27日の日本経済モデルの資料においても明記している。
一方で、基準としていたのは、年率1.6%を設定していたレファレンスであり、 前回の6.0%のGDPロスは、ベースとなる想定を低く設定していることと、 大幅な削減による活動量の低下の両方が影響している。
一方、今回の試算では、各ケースのベースとなるところは共通化した方がいいという指摘を受けた。 また、レファレンスケースにおいて想定よりも やや高いGDP(2005-2020年で年率1.3%と設定されているところが、1.5%となっていた)となっていたところを、 想定にあわせた方がいいという指摘も受け、レファレンスの活動をやや落として、BaUを作成した。 このように、今回の試算では、前回のようなレファレンスにおいて下駄を脱いだ状態で示すのではなく、 同じ経済成長率の想定を与えることとした。 つまり、今回の試算では、前回の変化のうち、ベースラインそのものを低く設定したというところを改め、 純粋に真水▲25%ケースの影響のみをカウントしたために、GDPへの影響は小さくなった。 - 可処分所得の減少幅について:前回44万円 → 今回17万円(一方で雇用者報酬は増加)
この点は、過去のタスクフォースでも話題にしたが、 可処分所得の定義そのものが大きく違っている。 前回(4月時点)では、炭素税収の家計への還流分を除いた「労働所得+資本所得」を 可処分所得と定義して計算を行った (4月までのワーキングチームで「労働所得+資本所得」を可処分所得とすると合意があったと理解したため)。 これに対して、今回は、タスクフォースの中で、炭素税収の還流分も家計の所得となるので、 これを差し引かないということを確認し、「労働所得+資本所得+移転所得」を可処分所得として定義した。 なお、他のモデルについては、前回も今回も、炭素税収も含めた定義で計算されているようである。
中間とりまとめでは、環境研の日本経済モデルの結果の一覧に 「なお、従前の定義による可処分所得の変化は、真水▲15%ケースにおいて▲2.6%、 真水▲25%ケースにおいて▲10.9%となる。」と注釈を加え、 削減幅が真水▲25%ケースにおいて大きくなっている(▲9.1%から▲10.9%)。
雇用者報酬の変化(マイナス幅が増加)については、上述の通り、 従前の定義における可処分所得の変化と同じ傾向を示しており、 可処分所得の変化と雇用者報酬の変化の傾向が一致しないという批判は当たらない。
| 中期検討委 選択肢⑤ |
タスクフォース ▲15% |
中期検討委 選択肢⑥ |
タスクフォース ▲20% |
|||
| 削減率① | (▲12.5%) | (▲12.9%) | (▲18.0%) | (▲17.4%) | ||
| 削減率② | (▲14.9%) | (▲15.3%) | (▲21.5%) | (▲17.4%) | ||
| 太陽光発電 | 3,700万kW | 3,700万kW | 7,900万kW | 7,900万kW | ||
| 風力発電 | 1,100万kW | 1,100万kW | 1,100万kW | 2,000万kW | ||
| 省エネ住宅 | 新築全て 既築の1割を改修 |
新築全て 既築の1割を改修 |
新築全て 既築の約5割を改修 (H4年基準を満たさない既築の全て) |
新築全て 既築の1割を改修 |
||
| 高効率給湯器 | 3,900万台 (ストックの約8割) |
3,410万台 (ストックの約7割) |
4,400万台 (ストックの約9割) |
4,160万台 (ストックの約8割) |
||
| 省エネ建築物 | 新築全て 既築の1割を改修 |
新築全て 既築の1割を改修 |
新築全て 既築の全てを改修 |
新築全て 既築の1割を改修 |
||
| BEMS | 全体の4割 | 全体の4割 | 全体の6割 | 全体の4割 | ||
| 従来自動車 | 保有燃費 18%改善 |
保有燃費 25%改善 |
保有燃費 12%改善 |
保有燃費 26%改善 |
エネ起CO2削減量=2020年エネ起CO2排出量-基準年エネ起CO2排出量
削減率①=エネ起CO2削減量/基準年GHG総排出量
削減率②=エネ起CO2削減量/基準年エネ起CO2総排出量


